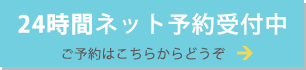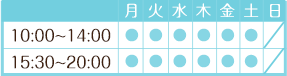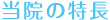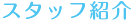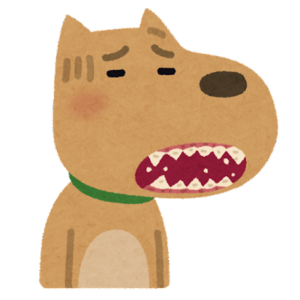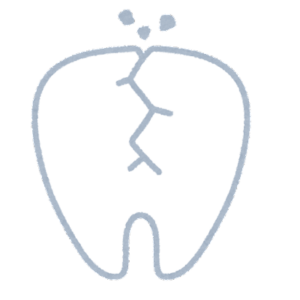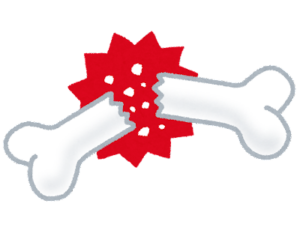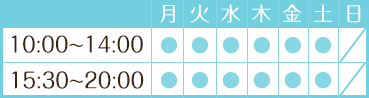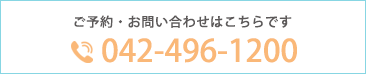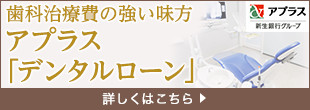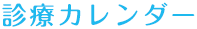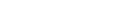こんにちは、清瀬いんどう歯科の町田です!(^^)!
ご自身のお口のにおいを嗅いだことはありますか❔
普通に過ごしていると、なかなかご自身で自分のお口のにおいを感じることは少ないですよね。
ですが、気付いていないだけで、周りの方からは「少し口臭がにおうかも・・・」と思われているかもしれません😥
今回はそんなことがないよう、口臭のセルフチェックの方法をお伝えいたします✨

1.コップのニオイをかぐ
コップの中に自分の息を吐き、そのにおいをチェックする方法です。
コップに息を吐いてから蓋をし、深呼吸をした後にコップの中の息のにおいを嗅いでみます👍
コップの代わりにビニール袋などでも代用できますが、その際は袋自体にニオイのない物を選ぶ必要があります💭
2.舌を見る
自分の舌を鏡で見てみましょう👅
健康な人の舌はピンク色をしていますが、舌に白い苔のような物がつくことがあります。
これを「舌苔」(ぜったい)といいます。舌苔がついている人は、口臭がある可能性があります😱
3.舌のにおいを嗅ぐ
2.で舌苔がついていた方はさらに舌のにおいも嗅いでみましょう。
コットンパフなどで舌苔を拭き取り、そのにおいを嗅いでみます。
自分でにおいが強いと感じた場合は口臭がある可能性があります😣
4.デンタルフロスのにおいを嗅ぐ
「デンタルフロス」を歯と歯の間に通したあと、そのフロスのにおいを嗅いでみましょう。
フロスが臭いと感じるなら、口臭がある可能性があります🌀
5.唾液のにおいをかぐ
唾液のにおいでも口臭はチェックできます。
唾液のにおいが臭いと感じたら口臭がある可能性があります😱
いかがでしたか?
口臭は普段ご自身では気付きにくいものです。
定期的にセルフチェックすることによって事前に口臭を防ぎ、爽やかなお口を目指しましょう🌟

InstagramTwitter @kiyose_indo